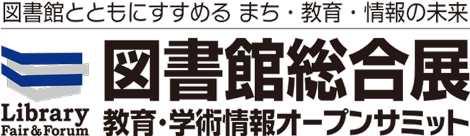図書館100連発-フツーの図書館にできること
日時:2012年11月20日(火)10:30-12:00
場所:第3会場
主催:アカデミック・リソース・ガイド株式会社
講師:
嶋田綾子さん(アカデミック・リソース・ガイド株式会社、いとか図書館ラボ)
嶋田学さん(瀬戸内市教育委員会 新図書館開設準備室長)
満尾哲広さん(フルライトスペース株式会社)
岡本真さん(アカデミック・リソース・ガイド株式会社 代表取締役/プロデューサー)
概要:「図書館を良くしていくには、どうすればいいのだろう?」ではない! 良い事業や工夫を実践している図書館は、すでにたくさんあります。その良や工夫を実践している図書館を幅広く紹介していくことが、いま求められています。 そこで、講演者が各地の図書館で集めた、さまざまな『きらりと光る』『小さな工夫』を一気にご紹介いたします。 たくさんの良い事例を知ることで、特別な図書館ではない、普通の図書館でもできる『小さな工夫』『良い事例』を学びあい、実践していきましょう。 なお、このフォーラムでご紹介する図書館の事例をまとめた冊子を、フォーラム会場と展示会場内のブースで販売する予定です。こちらもぜひお買い上げください。
フォーラム詳細:http://2012.libraryfair.jp/node/830
フォーラムの内容
- 「図書館100連発」嶋田綾子さん(アカデミック・リソース・ガイド株式会社、いとか図書館ラボ)
-
パネルディスカッション
その他の記録
「図書館100連発」嶋田綾子さん(アカデミック・リソース・ガイド株式会社、いとか図書館ラボ)
-
図書館の工夫や事例を100個紹介します!
- 読み知られることのあまりない小さな取り組みを、今日は紹介します
- それらを取り入れて、ぜひ図書館を良くしてください
-
100個の工夫を4つに分類する
- 資料提供の工夫
- 資料収集・保存の工夫
- 利用環境改善の工夫
- 地域・利用者連携の事例
- 個人発の図書館的サービス
-
総合的な改善のために
今回のレポートでは、図書館100連発で紹介された内容の一部を簡単に紹介します。残りの項目や詳しい写真などを含めた内容は、アカデミック・リソース・ガイド株式会社から出版されている「ライブラリー・リソース・ガイド 創刊号」に掲載されていますので、ぜひお買い求め下さい。
詳しくはこちら。
資料提供に関する工夫
1 ディスプレイでミニチュア本の展示
-
図書館の外に、特集として展示している図書のミニチュア本を作成して設置
-
コストをかけずに、インパクトを与えることができる
-
コストをかけずに、インパクトを与えることができる
2 Twitterと図書館内の連携
-
Twitterを使った図書館の連携
-
発信だけでなく、紹介した図書を展示している
-
発信だけでなく、紹介した図書を展示している
3 さまざまなスペースを使って、機動力のある展示
-
書架のちょっとしたスペースやカウンターなど、様々な場所で展示
4 子どもの成長にあわせて本を紹介
-
ブックスタートだけでなく、年齢に合わせて本を特集し、展示している
-
3歳児検診や小学校入学前だけではなく、25年以上読み継がれる本を25歳の絵本として紹介、次の世代に伝えることができる
-
3歳児検診や小学校入学前だけではなく、25年以上読み継がれる本を25歳の絵本として紹介、次の世代に伝えることができる
5 テレホンライブラリーの実施
-
電話をかけると図書の紹介を聞くことができる
-
テレホンライブラリーで紹介した図書を展示で紹介
-
テレホンライブラリーで紹介した図書を展示で紹介
6 本と物をあわせた展示
7 観光パンフレットも展示
-
被災地の新聞、写真、パンフレットなどを展示
-
観光連盟へ問い合わせるなど、図書館における情報提供の一つの形
-
観光連盟へ問い合わせるなど、図書館における情報提供の一つの形
8 観察と資料、ワンストップのサービス
-
希望すれば望遠鏡をレンタルでき、本の傍ですぐバードウォッチングができる
9 利用者の導線をつくり出す展示
10 書庫にある本の紹介コーナーを設置
-
書庫の本を展示
-
展示することで、利用を促すことができる
-
展示することで、利用を促すことができる
11 荷物用のロッカーを雑誌架に転用
-
荷物用のロッカーを雑誌架に転用
12 100円均一のワイヤーラックを活用
-
展示用品も100円均一用品で工夫
-
低コストでまかなえる
-
低コストでまかなえる
13 手製のブックスタンド 1
14 手製のブックスタンド 2
-
レシートの芯を重ねてブック用品にリサイクル
15 ハイレベルな手製のサイン
-
図書館員のお手製だが、デザイン性が高く見やすく・使いやすい
16 利用者参加型のPOP作成
-
利用者にPOPを書いてもらう
-
図書館だけでなく、市の広報誌でも紹介
-
図書館だけでなく、市の広報誌でも紹介
17 学生の手によるレファレンスPOPの作成
-
学生がレファレンスブックのPOPを作成
18 POPだけで本を紹介
-
本を展示せず、POPのみで紹介
-
POPを持って行くと、本を出してくれる
-
POPを持って行くと、本を出してくれる
19 利用できるソフトのパッケージを展示
-
ソフトウェアのパッケージを展示することで、利用者に見やすくアピール
20 本の見返しに本の帯を貼り付けて提供
-
情報の多い帯を捨てずに本に添付する
21 書棚のつくり方
22 館内案内板で展示のPR
23 血圧計の隣に関連本を展示
-
血圧測定の結果を、その場で本で調べることができる
24 定番児童書を平積みに配架
資料収集、保存に関する工夫
25 地域資料の収集
-
宮古島市立平良図書館
-
1館まるごと地域資料館
-
1館まるごと地域資料館
26 美術館と博物館が連携した地域資料の収集
-
展示図録を1,000点以上収拾
27 市の広報誌をデジタルアーカイブ
-
広報誌のデジタルアーカイブを図書館のウェエブサイトで公開
28 新聞記事をブログでデータベース化
-
記事の見出しをブログで公開することで、見やすくなり、データベースとして利用することもできる
29 掲示物で郷土資料を紹介
-
地域のゆかりの作家などを解説する資料を掲示
30 地域ゆかりの作家や作品のコーナーを設置
-
地域に関する知識が深くないとできない展示
-
丹念な調査による
-
丹念な調査による
31 地場産業をビジネス支援コーナーで応援
-
地場産業の専門図書館
32 ファッションライブラリーの設置
33 住民が集めた情報を、地域資料として保存
34 地域へ出て行き資料を作る
35 地域資料の収集についての分かりやすい呼びかけ
36 アーティスト情報と作品を同時に提供
-
アーティスト情報と作品をまとめて、図書館で提供
-
図書だけでない提供形態
-
図書だけでない提供形態
37 健康医療情報コーナーの徹底した棚づくり
-
関連するパンフレットの提供
-
新聞や、医療コミックなど、図書にこだわらない情報提供
-
新聞や、医療コミックなど、図書にこだわらない情報提供
38 アンケートに基づいた「雑誌入れ替え戦!」
-
購読雑誌の変更の際の利用者アンケートは、公共図書館では少ない
-
アンケートをとり、利用者の望む雑誌を購読する
-
アンケートをとり、利用者の望む雑誌を購読する
39 閲覧用パンフレットを手づくりで保護
40 出版PR誌の丁寧な扱い
-
出版PR誌を保存し公開することで、利用者へ出版情報を提供する
利用環境の提供
41 一人ひとりに居場所づくり
42 図書館内にBGMを流す
43 地元華道クラブの作品を館内に生ける
-
地域住民の活動の成果の発表
-
コストをかけずに館内を華やかにできる
-
コストをかけずに館内を華やかにできる
44 館内に生けた花をアーカイブ
-
生けた花を写真を撮影しアーカイブする
-
展示はしても、ここまでできるのは中々ない
-
展示はしても、ここまでできるのは中々ない
45 児童図書室に一般書を届ける
46 返本台の説明をわかりやすく
-
返本台を「やっぱり借りない本」と分かりやすく明示
-
利用者の使いやすさを意識した工夫
-
利用者の使いやすさを意識した工夫
47 靴音対策に履き替え用のスリッパを用意
48 携帯使用者のために電話ボックスを設置
-
電話ボックスを設置することで、外まで行かずに電話ができる
49 図書館に向かう開放空間で講座を実施
-
開放空間で講座を実施することで、気軽に立ち寄ることができる
50 図書館で町の無線LANを提供
-
街が無線LANを提供している
51 パソコン専用席にセキュリティー対策
-
盗難防止用のワイヤー設置のためのフックがつけられている
52 コピー利用時のトラブルを防ぐ掲示
-
コピー拡大の目安を示す張り紙
53 レファレンスコーナーに年号対比表を掲示
-
和暦・西暦対応表の掲示
54 分館所蔵の雑誌バックナンバーを展示
55 募集が終了したポスターも掲示
-
募集が終了したポスターを掲示し続けることで、人気があることを示すことができる
-
参加者へのフィードバックにもなる
-
参加者へのフィードバックにもなる
56 館内掲示物の頻繁な貼り替え
57 カードケースで配布物をきれいに保つ
58 禁止する理由の丁寧な説明
-
禁止する理由について詳しく説明することで、利用者に納得してもらえる
59 ICタグにメッセージを印刷
60 調べる方法のチャート図を作成
-
調べ物のサポートを利用者に見える形で提供
61 レファレンス事例を館内に掲示
-
図書館で、どのようなこが聞かれていることが一目でわかる
62 検索のミスマッチを防ぐための資料を提供
63 おはなし会を毎日実施
-
本館で毎日実施することで、いつ来てもお話会を楽しめる
64 人気本を複本購入し、1冊を閲覧用で提供
-
複本を館内専用にすることで、図書館に来ればいつでも読めるとアピール
65 本との出会いをつくり出す「としょかん福袋」
66 見せる移動図書館車
67 駅のコンコースにカウンターを設置
-
人通りが多いところに有人カウンターを設置
68 受け取り/返却ができる無人施設の設置
-
館外でも無人で受け取りが可能
69 24時間利用可能な貸出ボックス
-
利用者カードで受け取り・返却が可能
70 内側がのぞけるブックポストを設置
71 駐車場にブックポストを設置
-
駐車場にブックポストを設置することで、図書館までくる手間を省略できる
72 破損しやすい返却物に梱包材を提供
- 梱包材を提供することで、AV資料もブックポストで返却可能
73 コンビニエンスストアにブックポストを設置
地域・利用者連携の事例
74 利用制限や新サービスへの丁寧な説明
75 図書館まなびトーク
76 さばえライブラリーカフェ
-
地元の研究者など
-
講演者にとっても、講演をすることがステータスに
-
講演者にとっても、講演をすることがステータスに
77 地域にブックカフェを出前する
78 横浜入港の紅茶を提供
-
地域や現地の産業を大切にする工夫
79 駅のコンコースで読書活動を紹介
-
図書館に訪れることのない人にPRできる
80 図書館と専門機関が連携した技術書棚
-
技術書だけでなく、パンフレットなど技術資料を充実
81 近隣美術館と連携した企画展示
-
図書館だけでなく、美術館でもパンフレットの配布など、双方向のサービスを実施
82 図書館に併設する施設ブックリストを作成
83 隣接する科学館へ資料を提供
84 移動図書館に法テラスが同乗
-
被災地で、移動図書館に法テラスが同乗することで、郊外の人にも法律のサポートを実施
85 県立図書館のノウハウを広く提供
86 地元企業の製品を児童室に導入
87 図書館のしおりに子どもの絵を印刷
88 本の購入に市内本屋を斡旋
89 図書館利用カードで地域の活性化
- 図書館の利用者カードで商店街の割引実施
-
館内にはお見せのチラシを配布し、双方向でメリット
個人発の図書館的サービス
90 レファ協ほめまくり
91 リブヨ・ブログ
92 (短信)海外日本研究と図書館
93 図書館系ブログ集
-
図書館に関係する個人や、図書館のブログを紹介
総合的な改善のために
94 除籍雑誌を有償で利用者へ提供
-
リサイクルシール用代金を徴収し、安価で販売することで、図書を大切にして欲しいを考える
95 廃棄本をリサイクルして販売
96 レファレンス事例集を販売
-
展示だけでなく、販売も行なっていっる
97 図書館をよくするアイデアを学生に募る
- 図書館に関する意見を募集
-
実際に寄せられたアイデアから、改善やイベントを開催している
98 利用者が常に対話できる環境を提供
-
いつでも、館長と話をすることを受け付けている
99 ガラス張りの館長室
-
館長がどんな仕事をしているのか丸見え
-
館長以外でも、利用することができる
-
館長以外でも、利用することができる
100 さまざまな工夫を実践する図書館
- 小さな図書館でも、お金のない図書館でも、様々な工夫で図書館を良くすることができる
パネルトーク
(以下敬称略)
満尾/今発表した図書館に勤めている方、図書館のある自治体に住まわれている方はどれくらいいますか?
(十名ほど手が挙がる)
嶋田(綾)/図書館の数としては76館紹介している。
嶋田(学)/図書館同士であり、市民のみなさんであり、持ち寄って、わけあって工夫しているというのが通奏低音的にあるのではないか。
嶋田(綾)/いろんな図書館がいろんなことをやっている。みんな面白いことをしている。それがほんのちょっとしたことなので、非常にもったいないなと思っていた。
今回紹介したが、他の図書館でもやっている。「うちもやってる」と思った人は多いと思う。今回は自分の見た範囲でしかないが、他の取り組みがあれば、ぜひ紹介して欲しい。
満尾/色々と同じようなことをされている図書館さんはあると思う。そこをどうPRしていくか、アピールしていくかということが、図書館に求められている時代ではないだろうか。
学さんは瀬戸内市の図書館の新館を建設されているが、新館だからできること、既存館だからできることがあると思う。新館ではどのような工夫をなされているのか?
嶋田(学)/顧客志向ならぬ、当事者志向に目をつけて、図書館の方々はいろんな工夫をされている。瀬戸内では、郷土史を含めた情報をいかに自然に提供していくかを考えている。
郷土資料は、郷土史に詳しい人には良く利用されているが、あまり一般の方には利用されない。
街を知ることは、まずは歴史を知ることではないか。今回紹介された中で、現物を合わせて紹介している事例が興味深かった。瀬戸内市はかつて日本有数の塩田があり、塩造りをしていた歴史があった。また、塩造りに利用していた土器が発見されている。
このような、地域の時間の堆積を感じてもらえる物と資料をつくっていきたいと思う。
満尾/みなさんが思っていることとして、新しい取り組みは時間やお金が必要だと考えられていると思う。しかし、今紹介された事例は、ちょっとした工夫で行われているものが多い。
嶋田(綾)/基本的に今回紹介したものは、普通の図書館にできることということで、お金がかからないものが多い。電話ボックスの調達は難しいかもしれないが…明日からできることを多く紹介したつもりである。
経費や予算が足りないとか、どこもいっぱいいっぱいだと思うが、お客さんのことを考えて一手間かけるという工夫が大切だと思う。既存の図書館でも、どうすれば利用が良くできるのか、1番はお客さんの目線に立って考えること。いろんな工夫を聞いてみたい。
満尾/利用者としての住民と、図書館をつくっていく住民という2つの観点があると思う。瀬戸内市の取り組みはどうか。
嶋田(学)/図書館未来ミーティングという、ワークショップの手法を使って意見を頂いている。そこで、「大家族の間」という、3世代がくつろげる場所が欲しいとか、ドライブスルーでの貸出・返却など、どんどん新しい意見が出てくる。職員だけだと、様々な制約に囚われて発想が内向きになるが、市民の方に混じっていただくことで、新しい意見が出てくる。
満尾/ソーシャルメディアを使われている方も多いと思う。図書館にも利用するところが増えてきている。ソーシャルメディアの活用等々については何かあるか。
嶋田(綾)/途中で図書館ブログ集を紹介させていただいたが、ブログは図書館界のソーシャルメディアのはしりとしてまとめた。今はブログだけでなくTwitterやFacebookなど、ただ紹介するだけではなく利用者との双方向コミュニケーションや、出版情報や地域に関する情報を他のアカウントから引用し、一緒に本を紹介している。
ソーシャルメディアで写真を多用すると、カラフルで見ててすごく楽しい。きっとそれはお客さんも思ってくれる。新しい情報が発信されているという風潮は、良いことだと思う。
満尾/瀬戸内市でのソーシャルメディアの活用はいかがか。
嶋田(学)/ソーシャルメディアでは、地域の人が様々なものを見つけて、情報発信をしている。市民の方がつくったコンテンツを、図書館という場で面白く見せていきたい。
まず、市民の方が地域の魅力に気づき、それを発信するという仕組みをつくっていきたい。
満尾/会場の中で、先程出た中で、会場の中から語りたい人はいらっしゃいますか?
(司会から指名)
中津川市立図書館館長/公募で新図書館の準備をしていましたが、政争に巻き込まれ断念してしまいました。大変意気消沈しましたが、心機一転して、外装ではなく中身で、世界一になろうと決心いたしました。
お金もなく、理解もなく、難しいが事情もある。先日、利用者テーブルがなかったので新しく大きな利用者テーブルを準備した。これは、廃材を利用した天板に、木を切って足にして、総檜のものを用意した。政争があり分断されてしまった中で、読書を使って一つになりたいと思い、机のデザインは市の地形を模したものにしました。
献血を推進するなど、たくさん取り組みをして頑張っているところである。元気で頑張っているということをお伝えしたく、ポスターセッションも行なっている。
今日多く学んだ所を持ち帰って、もっと中津川の図書館を良くしていきたい。
国立教育政策研究所教育図書館/あまり知られていませんが、日本で最も教科書を持っている図書館です。お金もなく、人もないが、工夫できることはいっぱいあるなあと思う。いろいろやっているのでぜひ100連発に入れて欲しいと思ったが、教育図書館では、昔の紙を折って作る教科書造りを体験できる。他にも、教育研究論文索引を作成しているが、この索引作成はCiNiiよりも早く、2,3日でしてしまう。
ブース出展も力を入れているので、ぜひ来て欲しい。
満尾/最近は、カフェの入った図書館が多い。複合的な工夫もあるが、そこら辺はどうか。
嶋田(綾)/Twitterで図書館とカフェを募ったことがある。さすがに、図書館の中でコーヒーを飲めるのは全国で2館くらいだが、図書館のとなりにカフェを併設しているところは結構ある。
複合施設というとこまでいかないが、本と◯◯といった工夫ができると思う。また、本だけじゃなく、地域のアーカイブ機能を図書館は持っている。MLA連携ともいわれるが、もともと別れているわけではない。別れてしまったものが、今は元に戻っているのではないか。本だけでない情報を提供していく図書館というものの在り方が見えているのではないか。
満尾/今の、図書館と◯◯といったところで、瀬戸内市はいかがか。
嶋田(学)/一息ついて交流できる場所をつくりたいという声もある。一方で、図書館はそういうところじゃないという話もある。
他者と交流するにはどうすれば良いか。吉田先生がデンマークの公共図書館を紹介しているが、デンマークでは静かに本を読むスペースを、他にはチャットルームというしゃべる部屋をつくるケースがある。瀬戸内市でも、両方の要求がある。これをいかにゾーニングするか。工夫次第で、交流する仕組みをつくっていけるのではないかと考えている。
満尾/千代田区立図書館でも、ゾーニングの際に、飲食の飲だけでも認めるなど、賛否両論の中でこつこつと進めていった。いろいろと準備が大変だと思うが、進めていって頂ければと思います。
質疑応答・PRタイム
中津川市立図書館/中津川は和菓子の町でもあり、市内の和菓子屋さんに協賛を呼びかけ、図書館長のお点前でお茶会を開催した事例をご紹介したい。
南三陸町図書館/三度目の仮設の引越しがまもなく終わろうとします。今どういう状態かは、ここにいるみなさんはわからないと思います。町は、まだ何もありません。私は避難所に長くいました。上の人は、図書館よりまず復興だったが、全国からの多くの人の支援のおかげで仮設をたてることができた。バスも寄付していただき、循環もできるようになった。
まもなく、南三陸町・オーストラリア友好学習館、通称コアラ館ができる。図書館は約80平方メートルしかないが、少しずつ広さが加わって、全国の皆さんにご支援にいただいて、スタッフとともになんとか頑張っています。
南三陸町はまだ何もなく、これから冬場を迎えて、仮設で大変な寒さに耐える人がいるということを知って頂ければと思います。
最後に一言ずつ
嶋田(学)/LRG、発行されましたが、こういう情報を共有するのはすごく重要だと思います。
私が一番工夫うしなければいけないと思うのは、配架だと思う。利用者の動線に適応した配架を講じること。配架の工夫で10%貸出が増加した例もあります。タイトルを見せるなど、そういった工夫を行なって行きたい。
嶋田(綾)/今回は100個でしたが、まだまだ工夫はあると思います。100個、200個、1,000個、まだまだ集めて共有していきたいと思う。
今回の内容はライブラリー・リソース・ガイドで掲載しておりますので、ぜひお買い上げ頂ければと思います。
ありがとうございました。
(執筆:平山陽菜)