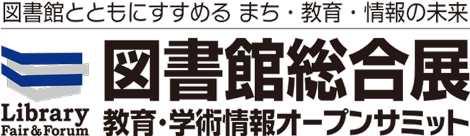図書館政策フォーラム「電子書籍時代の図書館ー次世代の文化創造に向けて」【第3部】
日時:2011年11月10日(木)15:35-17:00
場所:図書館総合展第9会場(会議センター301)
主催:図書館総合展運営委員会
講師:湯浅俊彦(立命館大学文学部准教授)
パネリスト:角川歴彦(角川グループホールディングス取締役会長)、田中久徳(国立国会図書館 電子情報企画課長)、
山中弘美(文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室長)、松田昇剛(総務省情報流通行政局情報流通振興課統括補佐)、
入江 伸(慶應義塾大学メディアセンター本部電子情報担当課長)、淺野隆夫さん(札幌市中央図書館業務化情報化推進担当係長)
第3部の構成
-
論点整理「電子書籍をめぐる諸問題ー出版業界と図書館界の利害調整の必要性」
- 1.出版界における電子書籍ビジネス
- 2.アップル、アマゾン、グーグルの戦略
- 3.電子書籍をめぐる図書館政策
- 4.図書館における電子書籍の導入事例
- 5.電子書籍時代の図書館の役割
- パネルディスカッション「図書館における実践的電子書籍活用法」
記録
当日の映像記録(Ustream)は以下の通り
配付資料
-
湯浅俊彦氏の発表スライド「論点整理」
湯浅俊彦(立命館大学文学部准教授)「論点整理」
出版界における電子書籍ビジネス
- 日本の出版販売額は2兆円を割り込んできている
- 出版販売額自体が下がってきている
-
離陸しない「電子出版」から2010年の「電子書籍元年」へ
アップル、アマゾン、グーグルの戦略
- 2010年=電子書籍元年アップル「iPad」の登場
- アマゾンはKindleというかたちでデータ通信機能を内蔵した端末を発売
- 当初から9万タイトルが米国で提供されている
- アメリカでは書店で売られているものがKindleで読まれている
- グーグルはGoogle eBooks
-
電子出版から巨大なデータベース
電子書籍をめぐる図書館政策
-
文化庁で電子書籍の流通に関する検討会議
- 国会図書館による送信サービスについて
-
著作権法の改正が行われる可能性が高い
- 権利制限規定を創設するように動いている
- 年内には決めていきたい
-
内閣府が知的財産戦略本部で話がまとまった
- 知的資産のアーカイブ化とその活用促進
-
電子書籍の流通* 利用* 保存に関する調査研究についてまとめた
- アンケート調査を行った内容をまとめた
-
国会図書館で大規模デジタル化が進んでいる
図書館における電子書籍の導入事例
- 従来からeブックを導入していた
-
NetLibrary
- 慶応義塾大学、iPadを貸与して書籍を閲覧してもらっている
-
大日本印刷 CHIグループ
- 堺市立図書館は初めてこのシステムを導入した
- 札幌市立中央図書館は特徴的
- 公共図書館における所蔵資料のデジタル化
-
図書館にとってはメディア転換できる資料をスキャニングして仕事をしている
電子書籍時代の図書館の役割
- 村上龍のように出版社とは別の流通経路で販売しようとする作家も現れてきている
-
まとめ
- 図書館における和書のコンテンツの利活用
- JapanKnowledge、NetLibrary→紀伊國屋書店
- どういうものを電子化してもらいたいと利用者は思っているのか
-
知覚障害の人に電子書籍を音声データで提供
パネルディスカッション
-
湯浅/それでは「図書館における実践的電子書籍活用法」とはなにか?
- 淺野さんは利用者にとってどういう視点で電子書籍を提供しているのか
-
淺野/図書館のサービスが初めて分かった。地域資料を積極的に集めていることが分かった
- ただそれを書架に配下して終わってしまっている
- 図書館は情報を発信していくべきだが、それが出来ていない
- 地域密着型の図書館にしたい
- 湯浅/地域情報ガイドやさまざまな地域マップ、出版社がやるような編集系作業、地域の情報を札幌市はデジタルでしかできないことをやろうとしているのか
-
淺野/観光客に対するスマートフォン元ネタは地域から
- この情報を有効活用していきたい
-
松田/片山総務大臣は図書館に対する熱い思いを語っていた
- 知の地域づくり、まずは図書館で勉強をして政策の企画立案をするべきだと強くおっしゃっていた
- 知の地域づくりに資するように地域住民にむけてICTを活用していって欲しい。
-
湯浅/慶応の文化解決型から課題解決型へ、むしろ出版されないものは図書館が情報発信していく
- これからの地域の役割と図書館とは?
- アクセスポイントしての図書館として山中さんに伺いたい、どのように扱われているのか
-
山中/公立図書館で役割について話し合ってもいる、公立図書館そのものについては社会教育機関という位置づけ
- 地域の歴史的資料を集めているなどしている
- その意味では地域の創造活動の貢献をしている。
- 国会図書館の資料をアクセスポイントにして利用しようという議論でまとまっている
- 湯浅/国会図書館では電子書籍になるとプリントできないなどの問題があると思うがどうか?
-
田中/今回、公共図書館への配信は、公共図書館も有料図書館を勉強する必要がある
- 一つ一つ許諾をとっていく
- 一方的に便利になることで出版ビジネスに支障が来してしまえば難しい
- 商業活動とどうバランスをとっていくかが問題
- 上手く信頼と共存して上手く連携していくかが大事
-
湯浅/対立というよう協調していく枠組みを作っていく必要がある
- 文芸書の貸出を巡って問題になり続けるのか
-
角川/ベストセラーを図書館に常備したいという思いが強くて、現在大量に仕入れている。
- 情報が固定化されて初めて知識になる
- 図書館の役割は知識を集めることだと思っている
- Twitterの情報は8割は消えていく、2割しか残らない
- 知識化するものが図書館にある、知の伝道するのが図書館
-
湯浅/イラン革命のときにビラやチラシを集めていた、それを集積することに意味がある
- 浅野さんは次の集積のために過去のデータを収集していると伺っている
-
淺野/ネットでどのように使うかが問題だと思っている
-
図書館は時間の感覚が違う
100年、50年のスパンで情報を持っておくのが図書館
-
図書館は時間の感覚が違う
-
湯浅/知の集積でいえば大学図書館が先端的なところを担わなくてはならない
- 大学図書館としても困難が見えてくることも見えてきた
- 国内コンテンツの電子化されていない部分に関してはどうか?
-
入江/学術書を買っているので、紙の本の売り上げをベースに考えている
- 図書館の予算は増えないので、大学は教育の研究スタイルが変わる中、新しいビジネスをつくる中で出版社とどのような関係になっていくかを考える必要がある
- 教育そのもに入っていかないとコストが出ないと思う
- 湯浅/出版社からしたらなかなか難しい、慶應さんは学生の利用を出版社に提供する具体例はあるか
-
入江/今の状態でいえば、電子を入れたからといって紙の売り上げが落ちることはない
- そもそも紙自体売れていない
- 1年生のみが紙の教科書を買い、2、3年生は紙の学術書を買わない
- 電子化しないと紙の本から逃げてしまうかもしれない
-
湯浅/電子化されていないことで、影響を受けるところもあるのではないか
- 淺野さんのインターネットを利用しなくてはならない状態で何が生み出されるか
-
淺野/これから考えていくところ
- 来年度から色々なデータベースを使えるようにしていく予定
-
湯浅/図書館は情報の拠点と言いながら無線LANも通っていない
- 松田さんはどう思うか?
-
松田/秋田県の図書館はデジタルアーカイブをしている
- 配信については実証実験をしているが、そもそも予算がない
- また、人材の問題を抱えている
- * 非常に短いスパンで人材が変わり、中々根付かない
-
湯浅/全国に先駆けてICTを変えることで効果が出やすいところもある
- 岡山市の話ではないが、ICTの活用を含めて検討を進めている
- 岡山はデジタル後楽園や様々なコンテンツが搭載されている
- 地方出版社によく会うが、みんなデジタルに弱い
- しかし札幌は図書館がデジタル化を推進しようとしているイメージがある
- 栄市の方教えて欲しい
-
会場/ほぼ札幌市と同じような考えで進めている
- 地域主導のデジタル化を推進している
- 現在は館内で閲覧出来るようにしている
- 一般家庭で見られるようにはしていない
-
湯浅/図書館を1回も利用したことのない人に対して、利用を促すために電子書籍を出しているところもある
- 萩市の図書館はどのような取り組みをしているのか?
-
会場/3月から電子書籍を公開している
- 地域アーカイブを公開する目的で使っている
- 今後公開が増えていけばと考えている
-
湯浅/コンテンツが増えないので利用者数が減っていくという側面もある
- コンテンツが増えないと図書館に導入するメリットがない、電子化は国会図書館に任せる流れなのか?
-
淺野/自分たちの本を電子化して売っていこうという流れがある
- 例えば、借りてもよし、買ってもよしというサイトがあっても良い
- 地域を大切にして欲しい
- 自分が昔作った本に愛情を持って欲しい
- このような本を図書館が未来永劫保存するべき
- このように作るアーカイブはとても魅力的
- 来年度はビジネスという文脈に乗せないと存続は難しい
-
湯浅/図書館から刺激を受けて出版するというのは面白い
- 大分県立図書館の俵さん、方向性としての電子書籍の展望は?
-
会場/電子書籍は、基本的に著作権の許諾をとれたところをパッケージとして図書館をPRする手段にはなる
- 著作権が消えていない書籍を扱うのは難しい
- 電子書籍のレンタルはマイナスになると思っている
- 地域情報のデジタル化はやらないといけないと思っている
- 国会図書館が出版物を電子化しているから良いが、大分県の地域情報は大分県がデジタル化する必要がある
- デジタル資料を一つのホストコンピューターで管理するにはお金がかかる
- 湯浅/これはアーカイブの話ですよね、地域資料について松田さんが担っている分野なのでは?
-
松田/知のデジタルアーカイブ、非常にコンフリクトがあるところ
- 基本的には一次資料のデジタルアーカイブをどうするかという議論を進めているところ
- 総務省はインターネット上のコンテンツを豊かにしようとしているところ
- 最近はネット上にない情報を、出版社が主導してデジタル化を進めてくれればありがたいと思う
-
湯浅/角川さん、出版社にとって自炊されることで誇りが傷つくこともあるのではないか?
- 商業出版社としての考えはどうか?
-
角川/相当の在庫を抱えているがそれを全てデジタル化するのは難しい
- 大きな負担になり、商業出版物の電子化はかなりきつい
- 利用権は与えるが許諾権は与えないという状態にある
- 所有権が個人に移ったわけだから、自身で買ったものを自炊するのは仕方無いと思う
-
湯浅/知覚障害者にとってテキストのデータ化は非常に重要
- アクセシビリティの問題としてどうか?
-
会場/全国の知覚障害者に音訳図書、点字図書を提供している
- 読みたいときに読めるのが一番の電子書籍のメリットだと考えている
- 湯浅/図書館への期待は何か?
-
会場/複製し、公衆送信ができるようになること
- そのためにも連携協力が大事だと考えている
-
入江/本には色んな種類があって、いろんなモデルがある
- それを考えないとどこへ行ってもぶつかってしまう
- 細かく議論しないと次は見えてこない
- 具体的目標と範囲に関して議論しなくてはならない
- 湯浅/丸善の小城社長、ここまでの流れで感想を下さい
-
会場/リプレイスしないことがもったいない
- これはチャンスだと考える、スマートフォンの力はすごい
- 出版業界における客はTwitterなどのサービスを提供するスマートフォンにとられてしまった
- セレンディピティ、書店としてのリアルな場が必要
- 湯浅/最後にひとことずつお願いします
-
田中/地域の公共図書館で地域のアーカイブを進めて欲しい
- 連携して検索できるようにしていければと思う
-
山中/当事者間の契約の中でそれなりの対価を払い、著作物をどのように流通させていくかが問題
- どんどん進展していくことを期待している
-
松田/紙と電子を合わせた出版市場という捉え方をアメリカではしている
- 右肩上がりで市場が伸びている
- 日本は4000の出版社がこの市場へ多く入っていってコンテンツを提供する必要があると考える
- 図書館が地域資料を含めICT化を進めていきたい
-
入江/慶應の学会誌など、いつでも利用出来るサービスはとても良い
- 学生はグローバル、それを僕らが押さえたとしても外へ出て行ってしまう
- これが大学の切迫感に
-
淺野/電子書籍によって本を広めていく時代に
- どんどんネットで本を広めていって欲しい
- 現在、図書館クラウドが全国的にできないかと考えている
-
角川/図書館と出版社とユーザーとの関係
- どのようにユーザーを捉えていくか
- コミュニケーションをお互いに図ることが大切
-
きちんと話し合う場を作ることを勧める
フォーラムをみた感想
昨年2010年は電子書籍元年だと騒がれ、様々なタブレット端末の市場進出に伴って一気に書籍の電子化の波が加速していきました。そのメリットを主張し、進んで電子化を進める流れが存在する一方、それに対し警鐘を鳴らす方もいるようです。
書籍を電子化することで、いくらでも複製できるようになり、一度により多くの人々に情報を提供できるようになります。
しかし一方で、それにより甚大な被害を受けるだろうと出版業界では予測され、何かと腰が重い気がしています。
また、図書館側でも電子図書館構想が進展する一方で、その電子化された書籍の利活用に関する議論は後を絶ちません。
利害対立という渦中において、図書館と出版業界、書籍の利用者との密な連携が今後はより一層必要になってくるだろうと考えています。
(執筆:梶浦美咲)